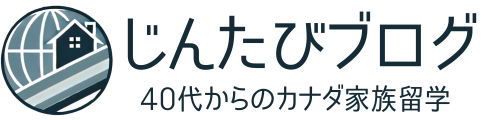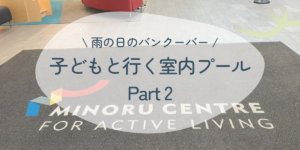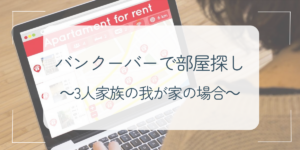退職に膨大なコスト?海外駐在中に会社を辞めた時の話
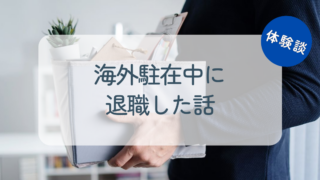
私は、カナダのバンクーバーへ家族とともに引越しをするタイミングで、勤めていた会社を退職してフリーランスへ移行しました。今回はその当時の退職に関する話を書いてみようと思います。
>>私たち家族のプロフィールをご覧になりたい方はこちら
家族でのカナダ行きを決めた当時、私は海外駐在でヨーロッパに赴任中5年目でした。海外駐在中の退職はその立場上、日本国内や海外でローカル直接採用で勤務しているときの退職と少々異なり、気にしなければいけないことが多くあり、より戦略的に進めなければいけないのが現実です。また、退職後に日本へ帰国する場合には、帰国にあたって発生する費用負担などについても、明らかに不合理な条件を会社から突きつけられないようにも気を付けたいところです。
退職してから一定時間経過したので、機密情報に抵触しない一般的な内容はそろそろ時効かなと思い、海外駐在中に退職するというのがどのような感じだったかを書いてみたいと思います。実際はケースバイケースかと思いますが、あくまで一個人の例としてご覧ください。
退職理由
私の退職理由説明はシンプルで、妻がカナダのバンクーバーのカレッジに留学をして勉強をするので、子育ても含めてその支援をするために帯同したいというものでした。
当時、仕事に関しては管理職として広い責任や裁量もあってやりがいもあり、人間関係も良好で、キャリア上も生活上も充実していて大きな不満やストレスは特にありませんでした。海外ビジネスや文化、英語環境などに順応できず鬱になってしまうケースなどはたまに聞くのでとても恵まれた環境だったと思います。
海外駐在中に退職する難しさ
どこで働いていても勤務先を退職するというのは、一定の大変さや面倒さを伴うのが常ではありますが、海外駐在中の立場で退職する場合は、さらに追加で考慮すべきことがあると感じます。例えば、
- 会社も時間・コストをかけて海外赴任者を用意しているので、人材・定期異動時期の観点で、後任者を簡単にすぐ当てがえるわけではない。そのため「辞めるので後は知りません」というスタンスは、より取りにくい。
- 海外駐在の人数は非常に少ないことが多いので、特に管理職の場合、本社との関係性を維持する必要がある日本人赴任者が抜けるインパクトが大きめ。特に他の日本人赴任者の負担が大きくなる可能性が高い。
- 海外駐在者には会社負担で生活サポートが入っていることが多いため、退職に伴って発生する費用関連(例えば引越し、帰国、家賃等)の負担がどうなるかを考慮する必要がある
- 駐在者に抜けられたら困ると、なかなか辞めさせてもらえないケースもたまに聞くので、すぐに辞められない場合もある
- 会社がサポートしているワークビザやその期間などの影響有無を認識しておく必要がある
というあたりでしょうか。
退職を伝えるまでの前準備
私の場合は、実は2年くらい前から家族で話し合いながら、今後のキャリア・家族・ライフスタイルの方向性やタイミングを探っていました。
当時の勤務先の人事制度は辞令制(事前打診等一切なしで会社が異動辞令を出して社員が基本従う仕組み)。また、海外赴任の場合は3年か5年で異動というケースが多く、かつ異動時期も期末の3月末・9月末であることがほとんどでした。私の場合、駐在3年目が終わったタイミングで異動がなかったので、恐らく5年終了後の可能性が高いかなぁと漠然と思っていました。
そのため、自身のキャリアや会社への影響などを考慮しつつ、赴任5年目が終了する期末を1つの起点として、そこで帰国の異動が出たら実行しようと決めて、妻と相談しながらスケジュールを引き、裏で妻の留学の計画と準備をしていました。
帰任辞令を気にせず先に退職希望を伝えてしまう、あるいは逆に辞令が出て日本に帰任してから退職を伝えるという手段もあったかとは思います。ただ、私はそのどちらの選択肢はとらず、帰任辞令が出るのを待ち、出た時点で退職を伝えました。理由としては以下の通りです。
- 会社や業務へのインパクトをできるだけ最小限に抑えたかった。
- できるだけ長い期間、海外駐在の状態で働いてキャリア経験を積み、かつ資金も厚くしておきたかった。
- 念のため、最悪のシナリオの場合に起こりうる下記のようなリスクを最小化したかった。
- 早く退職意思を伝えすぎることで、退職日まで長きにわたり嫌がらせを受けるリスク
- 不当に前倒しで退職させられたりするリスク
- 物価の高い現地生活において、生活の補助などを打ち切るなどの理不尽な対応や不利条件になるリスク
退職を伝えるタイミング
結果的に、退職日から5ヵ月前のタイミングで退職意向伝えた形となりました。
下記のような流れでした。
| 留学の計画と下準備をしておく |
| 赴任5年目の終わりごろ(2月)に新年度4月1日付での日本へ帰国の異動辞令(内示)が出る |
| ↓ 数日後、退職意思を伝える |
| ↓ その数日後、異動辞令(内示)が実質取消。海外赴任先でそのまま退職扱いに決定。 |
| ↓ 上司と最終出社日・退職日の合意 |
| ↓ 本社人事部へ退職申請手続き |
| ↓ 引継ぎ |
| ↓ 最終出社日 |
| ↓ 有給休暇消化(約1ヵ月) |
| 退職(5か月後) |
退職を伝える相手
私の場合は、現地に日本人上司がいたので(社長、同様に海外駐在の方)にまずは伝えました。そこから本社の部門、本社の人事部、現地の人事部などに順を追って情報が連携されました。まず誰に相談するかは、会社やその組織によって様々だとは思います。
幸い、上司はとてもいい方で、残念がられつつも最終的には理解を示していただき、特に不合理な引き留めや脅し、非難・中傷のような発言もなく、進めていただけました。ここが面倒なパワハラ系上司だったらもっとややこしいことになっていた気がします。
退職にあたっての会社との話し合い
退職にあたっては会社といくつか決めることがありました。
・いったん出た帰任辞令(内示)の扱い:
私の場合は次のステップまでまだ半年程度余裕があったので、海外の赴任先でそのまま勤務して退職でも、人が必要であれば辞令通り日本へ帰任して異動先で数か月仕事をしてから日本の本社で退職でもよいと伝え、判断を会社に委ねました。結論、帰任辞令(内示)は取消、海外赴任先でそのまま退職にする判断となりました。なお、帰国異動の内示取消は、業務上は大きく影響がないのですが、条件面で多少変わってくる要因となりました。
・退職日:
退職日については、比較的スムーズに決まりました。休みはあまりとらず働いていたので、有給休暇は余っていた30日以上のうち25日を使うことにし、先に最終出社日を4か月後と決めそこから25営業日後の5か月後を退職日にしました。有給休暇消化させてもらえないなどパワハラされるケースもたまに聞くので、まともな上司の方でよかったです。最終出社日後の1ヵ月間は雇用自体は海外に残っていましたが、特に業務上やることもないので、有給休暇に入った時点で日本へ帰国をして、退職日までは日本で過ごしました。
・社内関係者への通知
当時管理職で、複数チームの部下を持っていたこともあり、社内へいつどう伝えるかは上司と相談しながら進めました。日本本社の関係者にも限られた人以外にはまだ言わないように言われましたが、人事のうわさは本人が黙っていてもどこからか広がっているものです(笑)。時間経過とともに知っている人は多かったと思います。
ただ、帰国の異動辞令(内示)が既にいったん出ていたことで、現地企業スタッフから見れば、いずれにせよ去る人間としては変わりはなかったので、辞令を機に次のステップに行くという感じで、コミュニケーションとしてはネガティブなトーンはなかったと思います。
退職を伝える前に必ずやっておいた方がいいこと
- 就業規則、海外赴任規程を完璧に読み込んで理解する。特に、補助や費用に関する部分は何が規定されていて、何がされていないかを完全に理解しておく。
- 自身が関わっている業務や人に対するインパクトをある程度考えたうえで上司に話すストーリーやタイミングを決める。多くの場合は人が1人抜けたところで会社は変わらず回っていくというのが悲しい現実だが、人数がとても少なくすぐに替えが聞かない海外赴任者の場合は一定の配慮をきちんとしていることは重要。
- 会社、特に人事部門は、退職を伝えた時点で会社のコストを最小化することを最優先し、基本退職者には冷たい態度となるので、過度の期待はせず交渉するところは自分できちんと交渉する(そのために規程・規約をきちんと読み込んでおく)
- 条件などを交渉するときは、感情や気持ち・人道的にどうかなどではなく、規約や規程を基にして常にファクトかロジックベース。特に規程に明確に書いていない部分は、言いなりにならずきちんと交渉する。
- いくらスムーズにいく場合でも、結局人事周りは泥臭くなるので、一定の忍耐力や心の強さ、受け入れる柔軟性をもっておく。
帰任関連の費用負担
事前にネットで調べたり自身が経験した立場から感じることは、赴任中に退職を決意した海外駐在者にとって物理的ダメージが大きくかつ後からもモヤモヤが残りそうなところが、費用負担に関連した部分です。
会社によって異なるとは思いますが、会社の社命で赴任する海外駐在者は比較的条件が恵まれており、家賃補助などの生活費のほか赴任・帰任にあたっての往復の移動・引越し費用が会社負担であることが多いと思います。
一方で、海外駐在者が赴任途中で退職するとなると、次のような帰国に関連した費用が自己負担になる可能性を想定しておく必要があります。赴任先が遠方で家族人数も多い場合は、数十万~100万円越えになることも普通にあると思います。私の勤務先もほぼすべての項目が会社は出さないという扱い。うちは3人家族でしたので、100万円前後はかかりそうでした。
想定する費用
- 帰国のための費用
- 航空券代
- 国内移動の交通費
- 引越し費用(航空便・船便など)
- 現地の住居退去後~帰国日の数日のホテル代
- 日本到着直後の一時滞在先費用
- 住居関連(海外現地)
- 家賃精算関連
- 賃貸契約の早期解約等による違約金
- 退去にあたって必要な部屋クリーニング費用
- 住居関連(日本)
- 日本での賃貸契約の費用(仲介手数料など)
- 家電・家具などの買いそろえ
ネットを見ていると、他社でも辞める人には会社が帰国費用を出さないケースが多いようで、「理由にかかわらず社命の海外赴任の任務を終えて帰る事実は同じであるのに、なんで帰国費用が自己負担?」という怒りが多くありました。
ちなみに、私は規程を事前に読み込んでいたので「旅費(帰国のための移動にあたっての航空券や引越し関連部分)」は自己負担になりそうなことは事前にわかっていたので、基本そのまま受け入れました。一方で、本社人事部門が理不尽にも規程に定義がない部分までしれっと自己負担させようとしてきたので、そこは強く押し返し、交渉して会社負担に変えてもらいました。
できるだけ帰国費用を抑えるために取った方法
私の場合は、上司と退職について口頭とメール上で合意をしてから退職日までは5ヵ月あったので、実際に人事的な退職申請手続きをするタイミングまでには期間がありました。そこで、妻と子どもが先行して日本帰国することで、費用をできるだけ抑える手段を取りました。
規程に従うと、私の退職タイミングで家族全員が一緒に帰国すると、その費用がすべて自己負担になってしまいます。一方で、規程には、海外赴任期間に家族の呼び寄せ、家族だけの先行帰国という項目があり、その際は航空券や引越しに関して会社が費用負担支援をすると定義されていました。上司に「先に家族を帰してもいいですか?その場合はどうすればいいですか?」と聞いたところ、向こうから「会社の通常プロセスにのっとって手続きして」とだけ回答がきました(今考えると上司のやさしさっだったのかもしれません)ので、その制度を戦略的に使いました。
・妻、子ども
夫の最終出社日よりも数か月前(まだ海外赴任期間中の立場中)に先行帰国。海外赴任者の規程上の家族関連の制度を使い、航空券・引越し代は会社負担。そして、この引越し便(航空便・船便)にできるだけ荷物を突っ込む。
・夫
赴任先に1人で残り、最終出社日まで数か月間勤務し帰国。帰国費用はすべて自己負担。費用を抑えるため、航空券はマイルで手配、現地の家具・家電はほぼ全部売るか処分、服は断捨離し、海外宅配便は使わずスーツケース2個だけまでに荷物を絞って帰国。費用を最低限に抑えて帰国。
これにより、家族全員で自己負担で帰った場合であれば恐らく100万円前後かかっていたであろう帰国費用がだいぶ抑えられました。妻に数ヶ月間ワンオペ育児をお願いしなければいけない点がとても心苦しかったですが、夫婦で話し合ってそれが最適だろうという判断を下しました。
まとめ
ということで、ちょっとニッチな話ではありますが、海外駐在中に退職したら実際どうだったのかという話を書いてみました。
海外駐在の場合の退職は、日本国内で退職するより考えることがたくさんあります。特に帰国の費用負担面は死活問題です。ただ退職するだけで数十万~百万円以上コストがかかるなんて、コストが高すぎですよね。私は退職後も会社や同僚との関係性を良好に保ちたかったのでやりませんでしたが、黙って帰任してから帰国直後にすぐ辞めるという方が一定数いるのもなんだか納得できます。
余談
海外駐在は手当てがあったり生活支援があったり待遇面では比較的恵まれた環境にはあるので、豪華な生活や華やかなイメージ(毎週奥様はアフタヌーンティみたいな 笑)があるかもしれません。
ただ現実は、生活には困らないが豪華な生活には程遠いという感じで、日本人はもはや人件費の安い時代になりつつあることを日々感じていました。
確かに東南アジアや後進国などでは、まだリッチな生活のケースも残っているかもしれません。一方で、順調に給与が上がりつづけてきた欧米等の先進国での駐在に関しては、日本ベースの給与に手当てや物価加算がついているだけの日本人駐在員の給与はその国の給与水準ではもはや決して高くはなく、同じ役職レベルの現地スタッフの方が圧倒的に給与が高いこともざらでした(場合によっては、部下の方が年収額面は高かったり、その部下から給料安いからもっと上げろと交渉される悲しいことも...)。もちろん国や会社によるとは思うのですが。
以前は駐在vsローカルの給与格差みたいな議論もありましたが、スキルと経験そしてビザさえあれば、先進国においては今は海外ローカル現地採用の方が給与額面では有利な時代になりつつあるのかもしれません。
以上、長くなりましたが、カナダに来るにあたって海外駐在中に勤務先を退職をした話でした。私も「駐在中 辞める」で当時いろいろ調べて知識を蓄えたことを思い出して、自身の体験談をこの記事を書いてみました。誰かの役に立てばうれしいです。